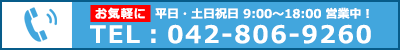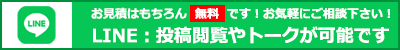地主として不動産事業を営むにあたっては税金による影響が大きいです。一般的には地主が支払う税金といえば、「相続税」というイメージがありますが、不動産を所有していることに関連して、以下のような税金も支払っています。
不動産に関連してかかる税金を整理すると、所有期間中は 固定資産税、都市計画税、(用途によっては)消費税 がかかり、一時的に(不動産購入) 不動産取得税、登録免許税、印紙税、不動産取得税、消費税(銀行借入)、印紙税、登録免許税、消費税(銀行手数料などにかかるもの) また、不動産事業において利益が出ていれば所得税や法人税、住民税や事業税などもかかり多種多様な税金との関わりが強いのが特徴です。
したがって、税改正による増税があれば不動産事業や承継において大きな支障が生じます。平成25年度の相続税改正(適用は平成27年1月1日以降)は、近年におけるオーナーさんを取り巻く税改正の代表的な事例といえます。
日本における人口は平成20年にピーク(1億2,808万人)を迎え、その後減少に転じています。 2050年代には人口は1億人程度になるものと推測されておりますが、ほかの経済予測などと比べて人口動態は将来予測を行いやすいと言われることから、おおむね予測どおりの結果になるものと思われます。ここ数年は全国平均で0.5%程度減少しており、一方で、東京都については人口が増加しており、その周辺地域においても下落率は緩やかです。 地主業においては、不動産賃貸収入にて事業を行っていることから人口動態による影響を受けやすく、 建物を建築する以上、長期的に建物からの収入を維持できる状況を目指さなければならず、「建物を建築して終わり」あるいは「不動産を購入して終わり」ではなく将来的な賃料収入の確保についても検討することが肝要です。 ただし、地方都市であるからといって、一律不動産事業が駄目であるということではなく、各地域によって事情は大きく異なることから日頃から不動産についての情報収集や分析が大切だと考えます。 また、リスク分散の観点から地元以外に不動産を購入するということも選択肢としては有効であると思われます。
地主業の後継者についても人口動態同様に今後課題が増えてくる可能性が非常に高い問題です。 よく地主業について「三代でなくなる」とのたとえがあります。この言葉の意味としてはいままでは相続税納税による資産の減少を指していましたが、今後は後継者不足により承継が途絶えてしまうリスクも含むように思われます。 したがって、今後の地主業の承継にあたっては子や孫の「直系卑属」のみならず甥や姪などの「傍系卑属」への承継が必要となる可能性が高くなります。 地主業においては、税金や不動産、金融の知識が総合的に必要となることから「直系尊属」に拘り過ぎると一族の衰退に繋がりかねません。したがって、これからは広く親族内で適正な後継者を選定するような取り組みが必要となると考えます。
今後の不動産事業においては「SDGs」に即した対応も必要です。持続可能な建物であることが、資産価値の防衛という観点でも不可欠で クリーンエネルギーや省エネ、永く使い続けられるような仕組みが必要であり、従来のスクラップ&ビルドではなく手を加えながら長期間に亘って利用していくような取り組みが必要になってきます。 建物自体のハード面のみならずSDGsには「平等」を謳った内容もあり例えば入居者に対する対応についても変化が必要です。
地主業にあたっては、多くの意思決定が発生します。 大きい点では「誰に承継をさせるか」ということであり遺言の作成にあたって意思能力の確認が不可欠です。そのほか、不動産の購入や売却、不動産の建築があり、それに伴う金融機関からの借入などで意思決定が必要である。 細かい点では、修繕の実施や、賃貸借契約の締結、管理契約など地主業を行うにあたって通常発生するような多くのことに都度意思決定を行っています。 意思能力に一切の問題がなければ日ごろ、そのような点に対して問題は無いと思いますが、いざ認知症になってしまった場合には、地主業に大きな支障が生じかねません。
厚生労働省によれば65歳以上の15%が認知症だそうです。 相続発生前に留意すべき点として認知症に対する対策、すなわち認知症になっても事業が継続できる仕組みづくりが必須です。
地主業の維持継続にあたって多くの問題を抱えています。その、ひとつひとつの事象を理解し、事前に備えておくことで円滑な承継が実現できますし、 地主業にあたっては家族構成や所有資産によって、それぞれが抱える事象が異なることから専門家などに相談をして現状把握をおこない健康なうちに対策を進めていくことが肝要です。
弊社は通常の足場による大規模修繕工事と無足場工法によるロープアクセス工事の両方をメイン事業としていますが、
空室対策、不動産管理、保険、士業の派遣などオーナー様の様々なお困りごとをトータルでサポートをしております。
相談は無料ですので、お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。